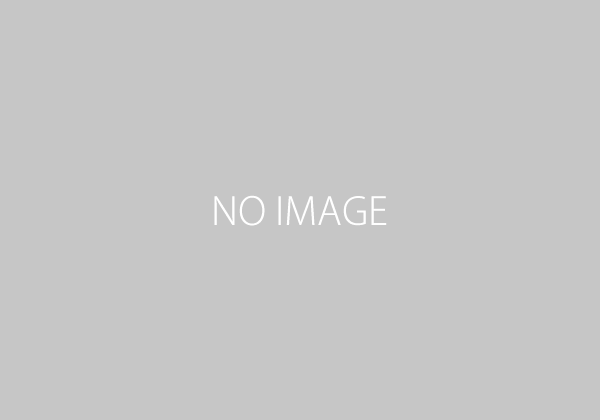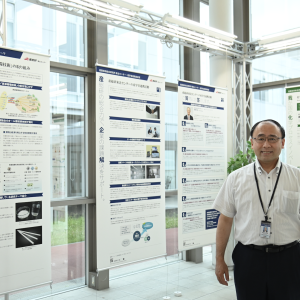産学連携の新たな形:トヨタ自動車東日本と東北大学が描く持続可能なものづくりの未来
VOL.70
トヨタ自動車東日本×東北大 「環境融和ものづくり」共創研究所
2022年4月、宮城県の地に画期的な研究機関が誕生した。トヨタ自動車東日本と東北大学が共同で設立した「環境融和ものづくり」共創研究所だ。従来の産学連携では、企業が抱える具体的な課題と大学の研究シーズをマッチングさせることが一般的だったが、この共創研究所では将来の社会像を描き、そこから逆算して研究テーマを創出するという、より包括的で長期的な視点に立った取り組みを展開している。トヨタ自動車東日本 総務部 未来共創推進部の主担当員であり、「環境融和ものづくり」共創研究所の運営統括責任者でもある東北大学 工学研究科 小池 亮特任教授にお聞きした。
■震災復興のプロジェクトを通じて生まれた革新的な共創研究所
「東北大学を拠点に、2012年より始まった震災復興に向けた文部科学省・復興庁の『東北発~プロジェクト』が立ち上がりました。当時、自動車の設計業務に従事していた私も東北大に出向してプロジェクトに参画。以来、研究の幅を広げてきました」と話す小池特任教授。
最初の研究は、「表面と接触面における科学技術」であるトライボロジーに関わる研究。機械のエネルギー効率、信頼性、耐久性など品質向上を目指すもので、機械の動く部分で発生する摩擦や摩耗などの現象を研究対象としている。特に自動車のエンジンの材料研究を推進してきた。さらに2019年には共同研究講座「先端自動車トライボロジー材料研究」を設立。省エネルギーを実現する材料研究を進めるとともに、より高効率なものづくり技術を目指し、ロボティクス分野での連携を行ってきた。
この共同研究を進める背景にはトヨタ自動車東日本の設立理念があるという小池特任教授。「トヨタ自動車東日本は東日本大震災を機に設立された企業なんです。被災した東北地域をものづくりを通じて元気にしたいという強い思いがあります。東北地域への連携や協働は社会貢献活動であるとともに、企業の根幹をなすミッションなのです。」

(トヨタ自動車東日本株式会社より提供)
そして、この理念のもとに進めれた共同研究が2022年4月1日、しっかりとした形になった。トヨタ自動車東日本と東北大学との連携による「環境融和ものづくり」共創研究所だ。
「築いてきた人材のつながりをさらに発展させることにより、将来の課題を地域とともに考える場にしたいという思いで設立しました」と話す小池特任教授。この共創研究所では、環境や高齢化などの将来課題に対し、産学に留まらず行政や地域とともに考え、循環型ものづくりを行うための基盤研究を行っている。その研究成果をもとに、人や環境と調和したものづくり技術を社会実装することを目指している。
■3つの領域で研究を推進
「環境融和ものづくり」共創研究所では具体的にどのような研究を進めているのだろうか。
「まずひとつ目のテーマが『省エネルギー』。自動車の燃費向上や信頼性向上とともに、生産設備などをより壊れないようにするための研究を行っています。2つ目のテーマが『共生ロボット』。安心安全に働ける環境づくりとともに、人のやりがいも向上させるロボティクスの研究を行っています。さらに、3つ目のテーマである『資源循環』では、より環境に優しくコンパクトなリサイクルや、廃棄物を有価物に変えて循環させる基盤研究やシステムの構築を行っています」と話す小池特任教授。
この3つの領域における議論を通じて、将来的な社会課題に対する研究テーマを抽出し、東北の資源・エネルギーの活用による持続的で柔軟なものづくりの実現を目指しているという。

運営責任者の足立教授と小池特任教授が、学内や地域、地域企業などとのコーディネートをしながら、「省エネルギー」「共生ロボット」「資源循環」の3つの領域における、多様な分野の人材との共創を行っている。
具体的な研究内容を紹介すると
①省エネルギーでは「腐食や摩耗の現象解明による安心・安全な機械の実現」。環境(水素・湿度等)による腐食抑制や摩耗・破損抑制の潤滑油の研究を通してCN設備の高信頼性・電池・ロボット等の寿命の延長を目指している。
②共生ロボットでは「複数台協調ロボットシステムによる人にやさしい工程づくりの実現」。選択肢や発想の広がりや人にやさしい、負担低減、やりがいを感じられる(自己効力感)という視点で、改善の道具として誰もが使えるロボット開発を目指している。
③資源活用・循環では、「塗装との界面制御による環境に優しい水を使ったバンパ塗膜剥離」。樹脂の再資源化を目指すとともに、自動車の工場から出る廃棄物をより簡便な方法で有価物に変える研究も推進している。
「この3つの研究の柱から、様々な先生方・他社・自治体の方々との連携を通じて研究の幅を拡大し、さらに地域社会への実装を目指して協業の可能性も探索しています」と小池特任教授は研究所の研究領域と目指す方向性について話す。

■異分野融合から、地域社会との連携へ
「13年間にわたる大学での研究活動を通じて培われたのは、単なる技術的な知見だけではありません」と小池特任教授は共創研究所の成果と可能性に広がりについて話す。「工学部から始まった人脈は、経済学部、文学部、情報科学、農学、医学といった多様な分野へと広がり、異分野融合による新たなイノベーションの土壌が生まれています。」
共創研究所の最も特徴的な側面の一つは、従来の枠組みを超えた異分野間の連携にあるという。例えば、自動車工場の排水処理では、既に一部に微生物処理が使われているが、さらにこれを発展させ、排水に含まれる金属などを微生物を使って回収するシステムの可能性も考えている。また、共生ロボットの研究では、安心安全ややりがいなど、人を対象にした研究でもあることから、脳神経や人間工学などの医学系の先生方や企業、経済学などの先生方との議論も行っている。
さらに共創研究所では、理論的な研究だけでなく、地域社会との密接な連携による実践的な取り組みも重視していることも強調する。
例えば、塗装が障害となってリサイクルが困難だったバンパーなどの樹脂部品について、水のみを使用した環境に優しい塗装剥離技術の開発が行われているが、このような樹脂の品質やリサイクルの課題は、地域の伝統工芸品の製造工程でもあり、この剥離技術や界面の分析手段を用いて課題解決に貢献できないか、漆器製造の企業とも議論も始まっている。
「地域との有機的なつながりにより、地域企業との協業も進み始めています。社内外とも連携して、より具体的な地域の貢献事例をつくっていきたいと思っています。」


■次世代人材育成と持続可能な成長モデル
共創研究所のもう一つの重要な使命は、次世代を担う人材の育成にある。2035年や2040年といった長期的な視点で社会の将来像を描く際、現在の若い世代が中心的な役割を果たすことになる。そのため、年齢や所属組織の壁を越えて、多様な若い人材が自由に発想し、チャレンジできる環境の提供が重視されている。
「企業内では目の前の業務に追われがちな若手社員も、共創研究所という場では、より長期的で創造的な思考を発揮できる機会が与えられる。大学という環境の中で、異なる専門分野の研究者や学生と交流することで、従来の枠組みにとらわれない新たなアイデアが生まれやすくなる」と共創研究所での次世代人材育成の効果を強調する。
大学の部門、地域企業の業種を問わず、分野横断的な産学連携活動を通し、多様な人材や知見の柔軟な交流を図り、将来のためのものづくりに関わる人材が育つ場として貢献している。


■未来社会への展望と継続的な発展
共創研究所の取り組みは、単発的なプロジェクトではなく、持続的な発展を目指した長期的な取り組みとして位置づけられている。研究成果の蓄積と人材ネットワークの拡大により、より多くの地域課題解決と新たなイノベーション創出が期待されている。
現在進行中の研究テーマから派生した他企業との共同研究も拡大しており、共創研究所が核となって産学官連携の輪が広がっている。この拡大する連携ネットワークは、東北地域全体の産業競争力向上と持続可能な発展に寄与する重要な基盤となっていくと期待されている。
「地域資源の有効活用、異分野融合による技術革新、次世代人材の育成、そして持続可能な社会システムの構築。これらすべてを包含した包括的なアプローチにより、真の意味での社会課題解決に貢献していきたいですね」と話す小池特任教授。
震災復興から始まった東北から発信されるこの革新的な取り組みは、今後産学連携の新たなスタンダードになるかも知れない。これからの持続可能な発展モデルとしても大きな意義を持っていると感じた。

トヨタ自動車東日本×東北大 「環境融和ものづくり」共創研究所
宮城県仙台市青葉区荒巻青葉6-6-10
HP:http://www.tribo.mech.tohoku.ac.jp/toyota-ej/index.html