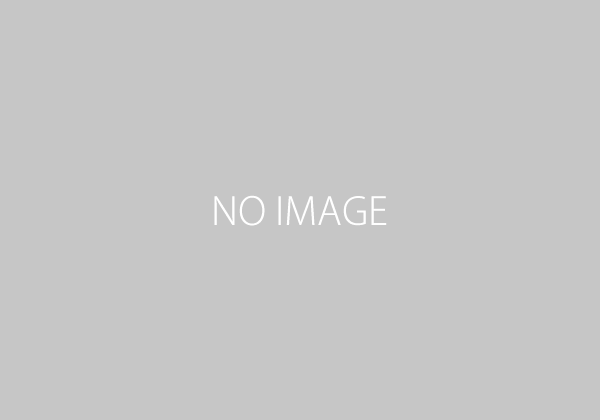挑戦と共創で「気仙沼のフカヒレ」を守り、発展させる。
Vol.19
株式会社石渡商店
三陸屈指の港町・気仙沼。宮城県の北東端に位置し、狭い湾や入り江、岬がノコギリの刃のように細かく複雑に入り組んだリアス海岸が見られる、漁業の盛んな地域である。そんな気仙沼は「サメのまち」としての顔も持ち、サメの水揚げ量、フカヒレ加工業者の数はともに日本一を誇る。今回取材した『石渡商店(いしわたしょうてん)』は、気仙沼一筋・フカヒレ一筋65年の専門店である。創業以来、2011年の東日本大震災をはじめ数々の困難を乗り越えながら「サメのまち・気仙沼」をリードし続けている存在だ。代表取締役の石渡久師社長に、フカヒレ製造への情熱や気仙沼に対する思いを聞いた。
創業者・正男さんの研究者魂が『石渡商店』のルーツ

『石渡商店』の創業は1957年。三代目にあたる久師さんの祖父・正男さんが、それまで研究員として勤めていた大手食品会社を退職後、家族とともに神奈川県から気仙沼へ移住。そのあとに開始した、乾燥フカヒレの製造や香港など海外への輸出事業が『石渡商店』のはじまりである。
創業当時から気仙沼は日本有数のマグロの水揚げ港でもあった。このマグロ延縄漁の混獲魚としてサメは水揚げされる。しかし、当時は生のヒレを”そのまま”乾燥させる(乾燥した状態のものを「原ビレ」という)以外の加工技術が開発されていなかったため、乾燥に向かない腹ビレや尻ビレなどの小さい部位は廃棄処分されるだけだった。


正男さんの研究者魂は脈々と受け継がれているようだ。
そんな状況を目の当たりにし、正男さんの研究者魂に火がつく。「捨てられるだけのフカヒレを活用することで事業を大きく発展させられるのではないか」と考えたのだ。やるべきこととして真っ先に頭に浮かんだのは、廃棄処分されるヒレを”生かす”こと。つまり、新たな製法の開発である。正男さんは、まず情報収集から動いていった。
「長く研究員として働いてきた祖父にとって、事前の情報収集はとても大事な作業だったのでしょう。自らの足を使って動いたり、人脈を使って詳しい人に聞いたり、あらゆる手段を使って情報を得ていたそうです。既存の情報の分析が、新しいモノや技術を生むヒントになる。祖父はそう考えていたのだと思います」。その言葉からは、祖父・正男さんの仕事に対する姿勢と、研究者魂への敬意を感じる。
新たな製法「スムキ」の開発。フカヒレの可能性を大きく広げる

正男さんが集めた情報の中に、やはりヒントはあった。それは、「原ビレ」の乾燥フカヒレを調理しようとするときには、お湯で戻すなどの「手間」がかかるということ。「これだ! この手間を省くような製法を開発しよう」という正男さんのひらめきから開発されたのが、生のヒレを”そのまま”乾燥させるのではなく、余計な皮や骨、肉を取り除いてから乾燥させる「スムキ」という方法だ。
この「スムキ」は、特に「家庭で手軽にフカヒレを調理して味わいたい」という一般消費者への配慮があるという点から、多くのフカヒレ製造業者に受け入れられた。そして今では世界共通の業界用語として用いられている。もちろん『石渡商店』の商標だ。
「気仙沼の会社が開発した加工法は、そんなにすごかったのか」と感心していると、久師さんは、「スムキ」が業界に吹き込んだ「新しい風」は他にもあると言う。
「『スムキ』は、フカヒレの食材としての可能性を広げることにも成功しました。生のフカヒレは、茶わん蒸しや刺し身など和食の食材としても活用することができます。かつてはフカヒレ料理と言えば「原ビレ」の乾燥フカヒレを使った中華料理しかなかったわけですが、それ以外の調理法を可能にしたのです」。
久師さんが言うとおり「スムキ」のフカヒレ料理は、世界中の美食家を中心に和食でも愛されるようになっていく。二代目・正師さんの代には、中国の来賓を迎える政府の晩餐会や、天皇即位を祝う宮中晩餐会で『石渡商店』のフカヒレが供されるなどして、目覚ましい成長を遂げていった。
三代目・久師さんの挑戦。震災で窮地に立たされたことが転機に


三代目社長の久師さんが『石渡商店』に入社したのは2002年、22歳のときのこと。久師さんは小学生から学生時代まで陸上競技に打ち込み、体育教師になることを目指した時期もあったが、やがて家業を継ぐ決意をする。
入社後は出荷品のラベルやシール貼りといった機械的な作業が主だったが、やってみて感じたのは「どんな作業や工程にもひとつひとつに意味があり、必要不可欠ということ」だと久師さんは言う。
何事にもポジティブに取り組む久師さんは、商品開発や販路開拓といった難しく重要な役割を次々と任されるようになっていく。当時の社長であり父でもある正師さんとともに、フカヒレ加工一筋の技術と開発力をもって「より使いやすく、より安心して利用してもらえる商品づくり」を推し進めた結果、徐々に販路は拡大。本場中国の料理店とも取引するようになり、事業は順調に伸びていった。
しかし、ちょうど久師さんが中国・上海へ販路開拓のため出張している最中の2011年3月11日、東日本大震災が発生。一転して会社は窮地に立たされる。
震災が発生した翌日、久師さんは成田に到着してから、友人のバイクに乗ったり、道中で偶然目にした自動車整備工場に頼み込んで車を借りたりしながら、ひたすら北を目指したそう。幸いにも家族全員、高台にある祖母宅に避難しており無事だったが、自宅兼工場は被災し、全壊となった。
「もう、たまらなく悲しかったですね」と語る久師さん。自分はポジティブな性格だと思っていたが、あまりにも辛く厳しい現実を前に、この時ばかりは落胆したという。
しかし、久師さんは正師さんや従業員たちの落ち込む姿を見て、やがて自分が先頭に立って再建を果たそうと決意をする。同じく『石渡商店』で働いていた弟の康宏さんと話をする中で「このピンチをチャンスと捉えよう」と、自らの発想を転換させていく。
「震災を機に、多くの人が気仙沼に注目するようになった今こそ、フカヒレブランドをPRすべき時ではないか、と考えました。震災という出来事は『石渡商店』にとってピンチをチャンスに変えるターニングポイント(転換点)だと思ったのです」。
この「発想の転換」をきっかけに、久師さんは会社再建に向けて動き出していった。
「気仙沼のフカヒレ」を、みんなで守り、盛り上げていく


やがて久師さんは、たしかな信頼関係で結ばれ、現在も気仙沼ブランドを共に推進するパートナーたちとの出会いを重ねていく。
そのパートナーの一人に、肉厚で濃厚なうま味が特徴の「もまれ牡蠣」の養殖漁師・畠山政也さん(通称やっくん)がいる。政也さんの「もまれ牡蠣」は”完熟牡蠣”としても知られており、3~5月下旬くらいの春時期に獲れる牡蠣のことを指す。春の牡蠣は雪解け水が川から流れ込んだ栄養豊富な海で育つため、身がしっかり入っていてクリーミーで濃厚な味わいになる。地元・気仙沼の人たちは、この春牡蠣が一年のうちで最も美味しいことを知っていた。そこで、外に向けて出荷し、春牡蠣の美味しさを広めようと道を開いたのが政也さんの父・政則さんだった。政也さんも、父に続いて「もまれ牡蠣」の生産とPR活動に取り組んでいる。
久師さんと政也さんが出会ったのは2018年のことだが、そのはじまりは2012年にまで遡る。まず、久師さんは2012年に「品質の良い牡蠣づくりを通じて唐桑を明るくする」をモットーに掲げ、気仙沼市唐桑半島で3代100年に渡り牡蠣養殖業を営んでいた『盛屋水産』と出会う。以来、その品質の高さから『盛屋水産』一本で仕入れをしていたそうだ。
しかし、2017年3月に起きた船の事故で主が行方不明となってしまった『盛屋水産』は、牡蠣養殖業の継続を断念せざるを得なくなる。新たな牡蠣の仕入れ先を探すことになった久師さん。翌年の2018年、『盛屋水産』と同じ品質を誇る「もまれ牡蠣」を紹介してもらったことで、その生産者の政也さんと出会うのだった。
久師さんが経験したさまざまな出会いは、新商品開発などに生かされていった。久師さんと『盛屋水産』の”唐桑の牡蠣”との出会いをきっかけに、2013年、新商品『気仙沼完熟牡蠣のオイスターソース』が生まれている。同商品はお土産としても人気を集め、「第24回全国水産加工品総合品質審査会 農林水産大臣賞(2013年)」を受賞。政也さんと出会った2018年以降は「もまれ牡蠣」を原材料に使用している。このほか、地場産品を使った商品の開発・販売や、フカヒレ業者の若手後継ぎで結成された「気仙沼ふかひれブランドを守る会」の発足など、久師さんを中心に「気仙沼を元気にする」という思いでつながった海の男たちは、現在も精力的に活動中だ。
これまであまり交流してこなかった同業他社ともしっかりつながり「気仙沼のフカヒレ」をみんなで守り、盛り上げていく。そんな久師さんの挑戦と共創の足跡を、これからも追っていきたいと思った。
「現在、自社でサメの肉を使ったペットフードの製造事業を計画したり、神奈川県のクラフトビール醸造会社の誘致プロジェクトに参画したりしています。フカヒレの高付加価値化を切り口として、気仙沼に異業種連携や共創のモデルをどんどんつくっていきます。そして、サメの水揚げがなくても稼げる、耐えられるくらいの経済基盤を築きたいと思っています」。
株式会社石渡商店
住所:宮城県気仙沼市松崎柳沢228-107
TEL:0120-108-537(フリーダイヤル)
0226-22-1893