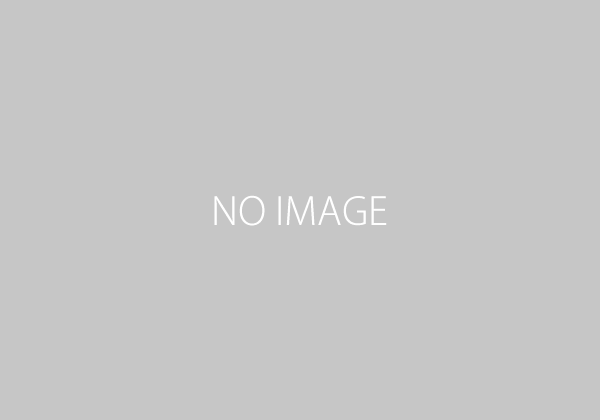地域に相応しい「産業」を!今ここにある資源を活用した農村産業づくりの先駆者
Vol.48
農業生産法人 有限会社 伊豆沼農産
宮城県仙台市から北に約70キロのところにある、ラムサール条約登録湿地「伊豆沼・内沼」。登米市と栗原市にまたがるこの沼は、古くは大沼とも呼ばれ、369ヘクタール(水面面積289ヘクタール)の広大な面積を持つ。夏は蓮の花が水面にたくさん咲き、冬には渡り鳥が飛来する自然豊かな場所だ。
(有)伊豆沼農産は、この伊豆沼のほとりで、「農業を食業に変える」を原点とし、「人」「もの」「環境」の価値を再発見しながら地域に相応しい「産業」を創造し続ける農業生産法人。代表取締役会長の伊藤秀雄さんへ多岐にわたる事業の戦略を中心にお話を伺ったが、その根底には地域への愛着や感謝といった「人のおもい」が脈々と流れていた。
付加価値の創出をテーマとした、食品の一貫生産販売システム

「自分たちが作ったものは加工販売も一貫して自社で行うべき」と語る代表取締役会長・伊藤秀雄さん。
伊豆沼農産は1988年(昭和63年)に創業。その事業展開は農業、食肉製品製造業、食肉販売業、食肉処理業、そうざい製造業、飲食店営業、農産物直売所運営、アイスクリームや酒類の製造等と多岐にわたる。
農畜産物の6次産業化に先駆者として取り組み、地域の農家と連携した食品の一貫生産販売システムを確立。そのほか、『伊達の純粋赤豚』をはじめ知名度の高いブランドを育てている。
「ちょうど家業である農業を父の代から私が受け継ぐときでした。創業当時は6次産業という言葉すらなかった時代です。自分たちが作り育てた農畜産物に自ら値段をつけることもしていませんでした。それってどうなのだろう?誰のためにどのようなものをお届けすれば喜ばれるのか、知る由もなかったのです。生産加工販売の一貫体制を組むことによって新しい農業経営が見えてきたのです」と伊藤さん。
一貫して生産販売を始めるにあたり、伊藤さんが必要不可欠なこととして考えたのは「付加価値を提供すること」だった。
そして、その付加価値とは農畜産物を「皿の上に乗せてお客様の口に入るまでのすべての工程を価値づけすること」だと考え、加工工場とともにレストランをオープンさせたのである。
このレストラン『くんぺる』のオープンを原点に、伊豆沼農産は6次産業のパイオニアとして、地域の「モノ」「コト」「ヒト」を最大限に活かしながら食品の一貫生産販売システムを確立するという、独自の取り組みを推し進めていくのだった。
地域の人たちの協力があるからブランドは生まれ、育つ

『伊達の純粋赤豚』をはじめとするブランド豚は数々の受賞歴を持つ。
食品の一貫生産販売システムの一環として注目すべきは、やはりブランド豚の開発だ。伊豆沼農産が生み出した赤豚をはじめとするブランド豚は、多くのファンから愛されている。
例えば『伊豆沼ハムシリーズ』は、創業間もない頃から続く看板商品の1つ。宮城県内で育てられた豚肉を用いて、ドイツマイスターの製造技術をベースにしながらも日本人に合った味付けを施したもの。
2002年(平成14年)デビューの『伊達の純粋赤豚』は、宮城県が8年の歳月をかけて改良した『しもふりレッド』という豚を純粋交配させて育てた豚である。やわらかい肉質が特徴で、脂の旨みが強く感じられる逸品だ。『伊達の純粋赤豚』は生産数(出生数)が少なく、飼育にも非常に手間がかかるため、地元の畜産農家たちの協力あってこそのブランドだそう。2004年(平成16年)には宮崎、福岡に次いで香港への輸出を成功させた。
さらに、2019年(平成31年)には新たに『伊豆沼豚』がデビュー。赤豚と同品種の『しもふりレッド』を父に持ち、赤身が鮮やかでやわらかい肉質が持ち味の新ブランド豚だ。
「2000年(平成12年)のドイツ農畜産業協会(DLG)や2006年(平成18年)のSUFFA2006、2019年(令和元年)IFFA(ドイツ国際食肉加工コンテスト)でも金賞を獲得し、世界的な食肉コンテストでの受賞は大変名誉でした。また、みやぎ食育大賞や東北ニュービジネス大賞など、農業分野のみではなく産業界のコンテストで表彰されたことも誇りに思います」と伊藤さんは今後のブランド豚の可能性に自信を覗かせた。
そのほか、豚肉以外にも甘酒、どぶろく、ジェラート、パンなども製造している伊豆沼農産。それらはみな、豊かな地域資源を生かした商品開発へのチャレンジである。
地域に相応しい「産業」の本質は、人の活性化にある

食農体験などができるラムサール広場では、地域の人たちが指導係として活躍。

本社に隣接する直売所は地元食材を求めて多くの客で賑わう。
伊豆沼農産が描いた6次産業の戦略に欠かせないのが、地域の「モノ」「コト」「ヒト」といった資源の活用だ。
「私たちの取り組みの目的は、農業を産業にすること。それが農業を食業に変えるということです。しかし、地域に目を向けてみれば高齢化が進み、とにかく若者がいない。自分たちの理想を実現させるためには、まずこの状況を受け入れることにしようと考えたのです」と伊藤さんは話す。
そこで考えたのが、高齢者にも合う仕事を創出することだった。地域の高齢者を『くんぺる』の厨房およびホールや直売所のスタッフとして起用したり、近年注力している食農体験などの観光事業にベテラン指導係として協力してもらったり。高齢者の生きがいづくりから、農村を元気にしていく機運を高めていったのだ。
「地域の高齢者が輝ける場所を創り、そこで元気に活躍する。そんな地域づくりこそが、この地域に最適な産業の創造に直結すると考えたのです。人の生きがいが、人を呼ぶ。そうすることで関係人口も創出できる。地域に相応しい6次産業の創造といっても、その本質は地域と人の活性化にあると思っています」。
さらに伊藤さんは、
「この迫町という地域は、とにかく人の良さがいいところ。人の良さというのは、インフラの充実や資源の豊富さで劣ったとしてもそれを補うだけの力があると思っています。例えばインバウンドが観光に求めることは、地元の人とのふれあいだったり、交流だったりします。人の良さが強みの迫町に合った産業を生み出すカギは、もともとそこに住んできた“人”にあったのです」と話してくれた。
少子高齢化は加速的に進んでおり、ここ10年で、「観念」だったものが「実感」に変わってきたと伊藤さんは言う。
高齢化率が上昇し、疲弊していく地域の姿を目の当たりにするからこそ、農村を元気にしたい、そしてそこにいる人を元気にしたい、とのおもいを強くしてきたのだろう。
大切なのは、自分たちの地域に必要な産業とは何か?を考え抜くこと

人を活かす農村産業。そのマニュアル整備を進める伊藤さん。
そして伊藤さんは、人を活かす産業のロールモデルを他地域にも展開しようと、マニュアルの整備を進めている。
「その地域に相応しい産業を創出する上で最初にやるべきこと。それは、自分たちの地域に必要な産業とは何か?を徹底的に考え抜くことだと思っています。そして、必要な資源やリソース、つまり地域の宝物探しについても、無いものを探すのではなく、あるものに新しく価値を見つけることの方が持続可能性の意味では重要です」。
「そしてそれら“あるもの”の良さを活かし、発信していくことが、仲間といえる“人”を呼ぶことにもつながる。仲間が集まればイノベーションを起こしやすくなり、また、ニーズも生まれる。こうして持続可能な産業というものは、つくられていくと考えます。この農村産業づくりのビジネスモデルを、なるべく早くマニュアル化して他地域へ提供する。この構想を、ぜひ実現させたいですね」。
農業を食業に変える。
この伊豆沼農産の理念は、農村産業という先進的なビジネスモデルに結実した。そしてさらに、自分たちが暮らす地域と同じ課題を抱える全国の仲間と、元気ネットワークを築いていきたいと思っている。
地域への恩返しという、農村産業づくりの原点を胸に
最後に、地域における農村産業に可能性を見出す伊藤さんご自身の原点と、根底に流れるおもいを聞いた。
「原点は、父が事故で亡くなり、自分が家業を継がなければならなくなったときですね。私は長男ですので、家業を継ぐのは当たり前とされる風潮が強かった。しかし、農業のことを勉強してきたわけではなかったので、これからどうしていけばいいのか、途方に暮れていました」。
「そんなとき、助けてくれたのがこの迫町の地域の人たちだったのです。田んぼの手入れや養豚の飼育管理まで、一つ一つを地域の人たちから教わりました。地域の人たちが自分を助けてくれ、育ててくれたのだと思っています」。
そんな伊藤さんが心に誓ったのは、「地域への恩返し」だった。そして地域の中に、農村の中に産業を創る。それこそが何よりの恩返しになる、と。
6次産業の先駆者として、誰よりも革新的に、農業界の第一線を走り続けてきた伊藤さん。
しかしその原点は、地域への恩返しという、他のどんなものよりもあたたかな「人のおもい」に包まれていた。
農業生産法人 有限会社 伊豆沼農産
住所:宮城県登米市迫町新田字前沼149-7
TEL:代)0220-28-2986 レストラン:0220-28-3131